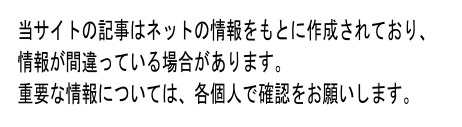日米修好通商条約とは?
日米修好通商条約は、1858年7月29日、日本とアメリカ合衆国の間で結ばれた通商条約です。江戸幕府が外国勢力との本格的な貿易を認めることとなったこの条約は、日本の外交史における画期的な出来事でした。欧米列強との交渉が進む中、日本は長らく続けてきた鎖国体制を徐々に放棄し、外圧により世界へと扉を開くことを余儀なくされました。
背景には、1853年のアメリカ艦隊(いわゆる黒船)来航があり、当時のアメリカ政府は日本との貿易を求めていました。その後、アメリカ総領事タウンゼント・ハリスが交渉を進め、ついに条約の締結へと至ります。日本側にとっては外交上の新たな局面であり、経済活動に対する大きな転換期でもありました。
この条約は、日本が自国の貿易における関税自主権を失い、アメリカに領事裁判権を認めるという内容を含んでおり、結果として後に「不平等条約」として批判されることになります。それでも当時の幕府は、外国勢力からの軍事的圧力や政治的混乱の中で、これを受け入れるしかなかったのです。
また、この条約はアメリカの全権代表であったタウンゼント・ハリスの名前を取って、「ハリス条約」とも呼ばれています。彼の粘り強い交渉と、日本の国内事情を巧みに利用した外交手腕により、条約が成立しました。この条約締結が、日本とアメリカの国際関係の基礎を築く最初の大きな一歩となり、以降の日米関係の礎を形成しました。
条約の条文には、日本が開港する港や貿易に関する取り決めが記されており、アメリカ側は関税面で優遇される立場となります。また、アメリカにとっては、日本市場の開拓という大きな経済的利益をもたらす一方で、日本側にとっては主権を侵害される形となり、不満と混乱を招く結果となります。
このように、日米修好通商条約は、幕末の日本における重大な転機であり、単なる貿易条約にとどまらず、政治、外交、経済にわたる広範な影響を持った歴史的出来事です。
条約締結の背景
日米修好通商条約が締結されるに至った背景には、19世紀半ばにおける日本と世界情勢の急速な変化が大きく関わっています。当時、日本は鎖国政策を続けていましたが、世界は急速に変化し、特に欧米列強がアジア市場に関心を示すようになっていました。
1. 黒船来航と日本への開国圧力
1853年、アメリカ合衆国海軍のマシュー・ペリー提督が率いる黒船が日本に来航しました。ペリーは日本の開国と貿易開始を求めるアメリカ大統領の親書を手渡し、日本に対して強い外交圧力をかけました。黒船来航は、日本にとって長年の鎖国体制を崩壊させるきっかけとなり、幕府はペリーの要求を無視できなくなりました。
これにより、1854年には日米和親条約が締結され、アメリカは日本に対する一定の影響力を確立しました。しかし、これでは十分ではなく、アメリカはさらに進んだ商業的権利を求めるようになりました。特に、日本が欧米諸国にとって潜在的な市場であることが明確になると、列強各国は競うようにして日本に開国を迫り始めます。
2. タウンゼント・ハリスの粘り強い交渉
黒船来航の後、アメリカから初代総領事として派遣されたタウンゼント・ハリスが1856年に下田に到着し、日米修好通商条約の交渉を開始しました。ハリスは、冷静かつ慎重な交渉者として知られており、ペリーとは異なる方法で日本との合意を目指しました。
ハリスは、幕府が鎖国政策を続けることがもはや時代遅れであり、日本が開国しなければ欧米列強の軍事的圧力にさらされる危険があると説きました。また、同時にアメリカが友好的なパートナーとして日本と共に歩むべきだという姿勢を示し、最終的に日本側の説得に成功しました。彼の交渉は15回にわたる長期に及び、幕府側は国防や内政の問題に頭を抱えながらも、最終的に条約締結に至ります。
3. 日本の内政と欧米列強とのジレンマ
幕末の日本は、欧米列強との貿易を進めるべきか、それとも国を閉ざし続けるべきかで大きな分裂を抱えていました。特に、幕府内では「攘夷(外国勢力を排除)」を掲げる尊攘派と、「開国」を進める開明派の対立が激化していました。
さらに、国防の問題も深刻でした。欧米列強の進んだ軍事力に対し、日本は軍事的には劣勢であり、直接的な衝突を避けるためにも、開国を通じて列強と友好的な関係を築く必要性がありました。幕府はこの状況下でアメリカとの通商条約締結に応じざるを得なくなり、外交的に不利な立場に立たされながらも、他国の侵略を避けるための苦渋の決断を迫られていたのです。
こうして、日米修好通商条約は、日本が鎖国政策を放棄し、世界の潮流に巻き込まれていく一歩となりましたが、それはまた、日本国内でさらなる政治的混乱を引き起こし、幕府の支配体制の崩壊を加速させる一因となりました。
条約の内容

日米修好通商条約は、当時の日本にとって不利な内容が多く含まれており、これが「不平等条約」と呼ばれる理由の一つです。以下では、条約の主要な内容を詳しく説明します。
1. 通商の権利
この条約によって、日本は特定の港を開港し、アメリカと自由な貿易を行うことを義務付けられました。具体的には、以下の港が開港されました。
- 神奈川(横浜)
- 長崎
- 兵庫(神戸) これにより、アメリカとの貿易活動が可能となり、アメリカ人商人がこれらの港に居住し、自由に取引を行えるようになりました。また、居留地が設けられ、アメリカ人がその範囲内で商取引を行うことが許可されました。ただし、日本国内全体を自由に移動できるわけではなく、旅行範囲は厳しく制限されていました。
2. 関税
関税自主権の喪失が、日米修好通商条約の最大の問題点でした。日本側は自ら関税を設定する権利を事実上失い、固定された低関税制度に従わざるを得なくなりました。具体的には、以下の関税が設定されました。
- 輸出品および輸入品に対して、一律**5%**の税率 これにより、日本の貿易における収益が制限され、さらに低い関税率のため、国内産業の保護も困難となりました。これは、列強諸国との不平等な貿易体制を強いられる結果をもたらし、後の日本の経済的自立を阻む要因となりました。
3. 領事裁判権
領事裁判権は、この条約の中でも特に日本側にとって不利な内容でした。領事裁判権とは、外国人が日本国内で罪を犯した場合、日本の法律ではなく、その外国人の国の法律で裁かれるという制度です。この条約に基づき、日本国内で犯罪を犯したアメリカ人は、日本の裁判制度ではなく、アメリカの領事館でアメリカの法律に基づいて裁かれることが義務付けられました。
これは、日本の主権を侵害する形となり、事実上、日本国内にアメリカの司法権が存在することを意味しました。一方で、日本人がアメリカ人に対して犯罪を犯した場合は、日本の法律で裁かれるため、法的な不均衡が生じました。この制度は、日本の主権を制限する不平等条約の象徴とされ、後年における日本の外交課題となりました。
このように、日米修好通商条約は、日本の開国を進める契機となった一方で、関税自主権の喪失や領事裁判権の導入など、日本の主権を大きく制限し、不平等な貿易体制を強いるものでした。この条約の内容は、後に日本が近代国家として主権を回復するために、多くの努力と時間を要することとなりました。
不平等条約としての側面
日米修好通商条約は、日本にとって非常に不利な内容を含んでおり、その結果「不平等条約」として歴史に刻まれました。以下にその不平等性を解説します。
1. アメリカに有利な内容で、日本の主権を制限
この条約はアメリカ側に非常に有利な条件を提供し、日本の主権を大きく制限しました。特に、領事裁判権の導入はその象徴です。日本国内で犯罪を犯したアメリカ人が日本の法律で裁かれることなく、アメリカの法律によって裁かれるという仕組みは、日本の法的主権を直接的に侵害するものでした。
また、アメリカは自由に貿易を行う権利を得る一方で、日本側は外部からの圧力を受け入れ、内政的に多くの制約を強いられました。これにより、国内の秩序を保つのが困難になり、開国による社会不安や反発が増大しました。
2. 関税自主権の喪失とアメリカへの最恵国待遇
条約では、日本は関税自主権を失い、輸出入に対する関税が一律5%に固定されました。これにより、日本は貿易によって国庫を潤すことが難しくなり、さらには国内産業の保護も困難となりました。貿易における関税は本来、国家が自主的に設定すべきものであるにもかかわらず、日本はその権利を事実上放棄させられました。
さらに、アメリカには最恵国待遇が与えられ、他国との貿易条件が改善された場合でも、自動的にアメリカにも同様の待遇が適用されました。これはアメリカが常に最も有利な条件で日本と貿易を行うことを意味し、日本にとって一方的に不利な条項でした。
3. 改税約書によってさらに不利な条件に固定された
条約締結後も、日本はさらに厳しい条件を押し付けられることとなりました。特に1866年に締結された改税約書では、関税がさらに低く固定され、輸出入の税率が一律5%に設定されました。この低関税は、結果として日本の財政にとって非常に不利な状況をもたらし、外国製品が日本国内に安価で大量に流入する一方で、日本の産品の競争力が削がれる原因となりました。
さらに、この約書によって条約改訂の機会も失われ、日本が望んでも関税率を見直すことが困難となりました。これにより、日本は不利な貿易条件を固定され、長年にわたって不平等な貿易体制を強いられることになります。
日米修好通商条約は、日本の開国の一歩ではありましたが、実質的には日本の主権を大きく制限するものであり、特に関税自主権の喪失やアメリカに対する最恵国待遇は、日本にとって非常に不利な条件でした。その後の改税約書によって、さらに不平等な条件が固定化され、日本がこの不利な立場から脱却するには、数十年にわたる外交努力が必要となりました。この条約は、日本の近代化に向けた重要な一歩であると同時に、日本が直面した国際的な圧力と主権回復への長い戦いの象徴でもあります。
条約の影響とその後の動き

日米修好通商条約は日本の開国を決定的にした一方で、国内に多くの混乱と反発を引き起こし、幕末の日本にさまざまな影響を与えました。以下では、条約締結後の日本国内の動きや、その影響について説明します。
1. 尊攘運動や外国船の砲撃事件などの反発
条約締結後、日本国内では外国勢力の影響力が増大することに対する強い反発が生じました。特に、幕末期の政治運動として知られる尊王攘夷運動(尊王:天皇を敬い、攘夷:外国勢力を排除する運動)は急速に拡大し、開国政策を進めた幕府に対する批判が高まりました。
これに伴い、外国船を攻撃する事件も多発しました。代表的なものとして、1863年に長州藩が下関で外国船を砲撃した事件が挙げられます。こうした攘夷行動は、逆に外国の報復を招く結果となり、幕府は列強から圧力を受け、さらに不利な条件での外交交渉を余儀なくされました。
2. 幕末の政治的混乱と桜田門外の変
条約締結に際して、国内では幕府内外で賛否が分かれていました。特に条約の締結が天皇の許可(勅許)を得ないまま行われたことは、朝廷や攘夷派の強い反発を招きました。条約を進めた井伊直弼は、これに対抗するために、反対派を弾圧する「安政の大獄」を実行しましたが、これがさらなる混乱を生む結果となりました。
1860年には、攘夷派の志士たちによって桜田門外の変が発生し、井伊直弼は暗殺されます。この事件は、幕末の政局に大きな衝撃を与え、幕府の威信は大きく揺らぎました。この時期から、幕府の権威が次第に低下し、政治的混乱が加速していきます。
3. 明治政府による条約改正交渉への動き
幕府の崩壊とともに、1868年には明治政府が成立し、外交の立て直しが急務となりました。明治政府は、特に不平等条約の改正を最優先課題の一つに掲げ、諸外国との交渉に取り組みました。しかし、最恵国待遇や領事裁判権などの不利な条件を改正することは容易ではなく、改正交渉は長期にわたって困難を極めました。
特に、日本側が関税自主権を失っていたことは大きな問題で、輸入品に低関税が適用され続けたため、国庫収入が制限され、国内産業の保護が難しくなっていました。また、外国人に対する領事裁判権の撤廃も重要な目標の一つでしたが、これを達成するにはさらなる外交的な努力が必要でした。
4. 1911年の日米通商航海条約でようやく関税自主権回復
明治政府は、不平等条約の改正に向けた長年の交渉の末、1894年に日英通商航海条約を締結し、まず領事裁判権の撤廃を実現しました。しかし、関税自主権の回復はなおも困難であり、その後も交渉は続きました。
最終的に、1911年に日米通商航海条約が締結され、ようやく日本は関税自主権を回復することができました。この条約により、日本は自主的に関税を設定する権利を取り戻し、長年続いた不平等な貿易体制に終止符を打つことができたのです。
日米修好通商条約は、日本の開国を促進するきっかけとなりましたが、不平等な条件が日本国内の反発や混乱を引き起こし、幕府の崩壊を加速させました。その後、明治政府が成立し、不平等条約の改正に向けた努力が続けられ、最終的に1911年に関税自主権が回復されるまで、長い道のりを要しました。この条約は、日本の近代化と国際社会への本格的な参加への布石でありながら、その過程で大きな犠牲を伴ったものでもありました。
日米修好通商条約の歴史的意義
日米修好通商条約は、日本の歴史において極めて重要な転機となりました。この条約が締結されたことにより、日本は長らく続けてきた鎖国政策を放棄し、世界との貿易と交流を開始することになりました。これが後の明治維新への道筋を開き、日本の近代化や国際社会への参加を促すきっかけとなったのです。
一方で、この条約は日本にとって不平等なものであり、主権を侵害した不平等条約としての側面も強調されなければなりません。特に、関税自主権の喪失や領事裁判権の導入は、日本が外国勢力に対して自主的な外交・内政を行うことを困難にし、日本の主権を大きく制限するものでした。
このように、日米修好通商条約は、日本が国際社会に踏み出す重要な一歩であると同時に、長年にわたって不平等な条件を受け入れる苦しい道のりの始まりでもありました。日本が条約改正を達成し、主権を回復するまでの約50年間にわたる努力は、この条約がもたらした負の側面と、その克服に向けた日本の近代化への執念を象徴しています。