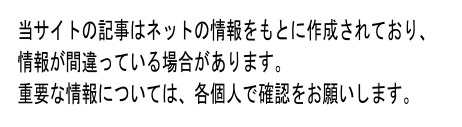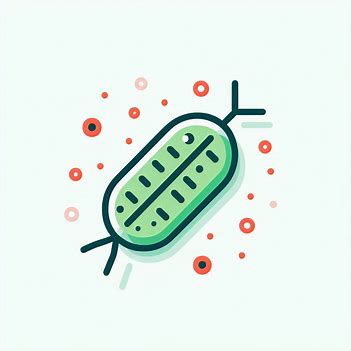
はじめに
プランクトンは、水中を漂いながら生活する微小な生物群であり、海洋や淡水環境において極めて重要な役割を果たしている。光合成を行う植物プランクトンは、地球上の酸素の約50%を生産するとされ、食物連鎖の最下層として動物プランクトンや魚類、クジラなどの多くの生物の餌となる。一方、動物プランクトンは、魚類や海洋哺乳類の主要な栄養源となり、水界生態系のバランスを支えている。
プランクトンは、水温や光、栄養塩の濃度などの環境要因に大きく依存しており、その分布や生態は気候変動や海洋環境の変化と密接に関係している。例えば、海水温の上昇や富栄養化によって特定のプランクトンが異常増殖すると、「赤潮」や「アオコ」といった現象が発生し、水質悪化や生態系の破壊を引き起こすことがある。
また、近年の科学技術の進展により、DNA解析や蛍光測定技術を活用したプランクトン研究が進み、より詳細な分類や分布解析が可能になっている。これにより、環境変動の指標としてのプランクトンの役割が注目され、気候変動や海洋酸性化の影響を評価するための重要な手段として利用されている。
本記事では、プランクトンの定義や分類、生態系における役割、分布の要因、研究方法について詳しく解説する。プランクトンの生態を理解することで、水界環境の変化を捉え、持続可能な海洋資源管理や地球環境の保全につなげることができる。
プランクトンの定義と分類
プランクトンとは、水中に生息しながらも自力で水流に逆らって移動する能力を持たない生物の総称である。多くのプランクトンは微小な生物であり、湖、河川、海洋などの水域に広く分布している。
プランクトンの分類にはさまざまな方法があるが、一般的には以下の3つの視点から分類される。
- 栄養摂取の方法(植物プランクトン・動物プランクトン・細菌プランクトンなど)
- 生活史(終生プランクトン・一時プランクトン)
- サイズ(メガプランクトン・マイクロプランクトンなど)
これらの分類を通じて、プランクトンの多様な特徴や生態的役割を理解することができる。
プランクトンの語源と歴史
プランクトンという名称は、1887年にドイツの海洋生物学者ヴィクトル・ヘンゼンによって命名された。語源はギリシャ語の「πλανάω(planáō)」で、「漂流する」「さまよう」という意味を持つ。この語源が示すように、プランクトンは水の流れに身を任せて漂う生物である。
プランクトン研究の歴史は古く、19世紀にはすでに海洋学者たちがプランクトンネットを用いた採集を始めていた。その後、20世紀に入ると顕微鏡技術の発展により、微小なプランクトンの構造や生態がより詳しく解明されていった。
近年では、分子生物学や遺伝子解析の技術が進展し、プランクトンの種分類や生理機能の研究が飛躍的に進んでいる。特に、海洋における炭素循環や酸素生産におけるプランクトンの重要性が再認識されている。
浮遊生物としての定義
プランクトンとは、水中に浮遊し、自力で移動できない、もしくは移動能力が極めて低い生物群を指す。一般的に、魚類や哺乳類のように自由に泳ぎ回ることができないため、水の流れに従って移動することが特徴である。
プランクトンには、以下のような特徴がある。
- 水流に逆らう力がほとんどないか、非常に弱い。
- 光合成を行う植物プランクトン、他の生物を捕食する動物プランクトンなど、多様な栄養摂取の方法を持つ。
- 微生物から大型のクラゲまで、さまざまなサイズの生物が含まれる。
また、一部の生物は幼生時にはプランクトンとして浮遊するが、成長すると底生生物(ベントス)や遊泳生物(ネクトン)に移行することもある。
水生生物の分類(プランクトン・ネクトン・ベントス・ニューストン)
水生生物は、その生活様式に基づいていくつかのグループに分類される。プランクトンはこれらのうちの一つであり、他にも以下のような分類がある。
- プランクトン(Plankton):水中を漂う生物で、水流に逆らう力を持たない。
- ネクトン(Nekton):水流に逆らって自由に泳ぐことができる生物(例:魚類、イカ、海洋哺乳類)。
- ベントス(Benthos):水底に生息し、そこに固着または活動する生物(例:貝類、ウニ、カニ)。
- ニューストン(Neuston):水面の直上または直下に生活する生物(例:アメンボ、クラゲの一部)。
この分類は、各生物の生態的役割を理解する上で非常に重要であり、特に海洋生態系の構造を把握する際に役立つ。
プランクトンの種類と分類法
プランクトンは、その多様性からさまざまな方法で分類される。主に「栄養摂取の方法」「生活史」「サイズ」の3つの基準に基づいて分類され、それぞれのグループが異なる生態的役割を持つ。
植物プランクトンは海洋の生態系において一次生産者として機能し、動物プランクトンはそれを捕食する。さらに、細菌プランクトンやウイルスプランクトンは水中の分解過程に関与し、栄養循環に重要な役割を果たす。また、プランクトンの中には、幼生期のみ浮遊するものや、一生を通じてプランクトンとして過ごすものもいる。
栄養摂取の違いによる分類
プランクトンは栄養の取り方によって大きく分けることができる。主に「植物プランクトン」「動物プランクトン」「細菌プランクトン」「ウイルスプランクトン」の4つのグループが存在する。
植物プランクトン(光合成を行う)
植物プランクトン(Phytoplankton)は水中で光合成を行い、酸素を供給するとともに、有機物を生産する生物群である。植物プランクトンは海洋や湖沼の生態系における一次生産者であり、多くの動物プランクトンや魚類の幼生の餌となる。
代表的な植物プランクトンには以下のようなものがある:
- 珪藻(けいそう, Diatoms) - ガラス質の殻(フラストゥル)を持ち、シリカを主成分とする。
- 渦鞭毛藻(うずべんもうそう, Dinoflagellates) - 一部は赤潮を引き起こすが、光合成を行うものも多い。
- シアノバクテリア(Cyanobacteria) - 藍藻類とも呼ばれ、最も古い光合成生物の一つ。
- 円石藻(えんせきそう, Coccolithophores) - 炭酸カルシウムの殻を持ち、大規模な白亜の堆積を形成する。
動物プランクトン(摂食による栄養摂取)
動物プランクトン(Zooplankton)は他の生物を捕食することで栄養を得るプランクトンであり、食物連鎖において重要な役割を担う。植物プランクトンを摂食する種もいれば、他の動物プランクトンを捕食するものもいる。
代表的な動物プランクトンには以下のようなものがある:
- カイアシ類(Copepods) - 海洋に最も多く存在する甲殻類の一種で、魚類の幼生やクジラの餌となる。
- クラゲ(Jellyfish) - 遊泳能力が低いためプランクトンに分類されるが、肉食性で他の小型生物を捕食する。
- オキアミ(Krill) - 南極海などに生息し、ペンギンやクジラなどの重要な餌となる。
細菌プランクトン・ウイルスプランクトン
細菌プランクトン(Bacterioplankton)は有機物を分解し、栄養循環を助ける微生物群である。ウイルスプランクトン(Virioplankton)は、バクテリアや他のプランクトンに感染し、分解を促進する役割を持つ。
細菌プランクトンの代表例:
- プロクロロコッカス(Prochlorococcus) - 地球上で最も多い光合成生物であり、海洋の炭素循環に貢献する。
- サルモネラやビブリオ属 - 一部は病原菌としても知られるが、水中の分解過程に関与する。
ウイルスプランクトンは、海洋生態系において微生物の増殖を抑制し、物質循環を促進する役割を持つ。
生活史による分類
プランクトンは生活史の全てをプランクトンとして過ごすもの(終生プランクトン)と、一部の期間のみプランクトン生活を送るもの(一時プランクトン)に分けられる。
終生プランクトン(生涯を通じてプランクトン)
終生プランクトン(Holoplankton)は、生涯を通じてプランクトンとして漂う生物である。代表例として、カイアシ類やクラゲが挙げられる。
一時プランクトン(幼生期のみプランクトン)
一時プランクトン(Meroplankton)は、幼生期のみプランクトンとして浮遊し、成長すると底生生物(ベントス)や遊泳生物(ネクトン)になる生物群である。例として、ウニやカニの幼生がある。
サイズによる分類
プランクトンは、その大きさによって分類される。最も大きいものはクラゲのようなメガプランクトン、最も小さいものはウイルスプランクトンに相当する。
- メガプランクトン(Megaplankton):20cm以上(例:クラゲ)
- マクロプランクトン(Macroplankton):2-20cm(例:オキアミ)
- メソプランクトン(Mesoplankton):0.2-20mm(例:カイアシ類)
- マイクロプランクトン(Microplankton):20-200μm(例:珪藻)
- ナノプランクトン(Nanoplankton):2-20μm(例:小型藻類)
- ピコプランクトン(Picoplankton):0.2-2μm(例:シアノバクテリア)
- フェムトプランクトン(Femtoplankton):0.2μm未満(例:ウイルス)
プランクトンの生態系における役割

プランクトンは、水界生態系において非常に重要な役割を果たしている。食物連鎖の基盤を形成し、酸素の供給、炭素循環など、生命の維持に不可欠な機能を持つ。特に、海洋のプランクトンは地球規模の生態系に大きな影響を与えており、その動態は気候変動や海洋環境の変化とも密接に関連している。
食物連鎖の基盤としての役割
プランクトンは水生生態系の食物連鎖の最下層に位置する。植物プランクトンが光合成によって生産した有機物を動物プランクトンが摂食し、それをさらに魚類やクジラなどの大型生物が捕食するという構造が成り立っている。
この食物連鎖の基本的な流れを以下に示す:
- 植物プランクトン(光合成によって有機物を生産)
- 動物プランクトン(植物プランクトンや他の小型プランクトンを捕食)
- 小型魚類・甲殻類(動物プランクトンを捕食)
- 大型魚類・海洋哺乳類(小型魚類や甲殻類を捕食)
このように、プランクトンが存在しなければ、海洋生物のほとんどが生存できなくなるため、その役割は非常に重要である。
光合成による酸素供給
植物プランクトンは、陸上の植物と同じように光合成を行い、大量の酸素を生産する。実際、地球上の酸素の約50%以上は海洋の植物プランクトンによって供給されていると考えられている。
光合成の基本的な反応式は以下の通りである:
6CO₂ + 6H₂O + 光エネルギー → C₆H₁₂O₆ + 6O₂
この過程で生成された酸素は、水中の生物に供給されるだけでなく、大気中に放出されるため、地球の大気組成の維持にも重要な役割を果たしている。
代表的な酸素供給源となる植物プランクトンには以下のようなものがある:
- 珪藻(Diatoms) - 海洋における酸素生産の大部分を担う。
- シアノバクテリア(Cyanobacteria) - 古代から存在し、光合成による酸素供給の歴史を作ってきた。
- 円石藻(Coccolithophores) - 二酸化炭素を吸収しながら酸素を供給する。
特に、光合成による酸素供給は、気候変動の影響を受けやすく、プランクトンの減少は地球全体の酸素バランスにも影響を与えるため、環境保護の観点からも重要な研究対象となっている。
海洋の炭素循環への影響
プランクトンは、炭素の循環を促進し、大気中の二酸化炭素(CO₂)を吸収することで、気候変動の緩和に寄与している。特に、植物プランクトンは光合成を通じてCO₂を取り込み、海洋の炭素固定に大きく貢献している。
この炭素循環のプロセスは以下のように進行する:
- 植物プランクトンがCO₂を吸収し、有機物として蓄積
- 動物プランクトンが植物プランクトンを捕食し、その一部をエネルギーとして消費
- 死んだプランクトンや排泄物が沈降し、深海に炭素を蓄積(生物ポンプ)
- 一部の炭素が分解され、海洋中に再放出されるが、大部分は深海に蓄積
この「生物ポンプ」と呼ばれるプロセスにより、大量の炭素が深海に運ばれ、長期間にわたって隔離されることになる。この炭素固定がなければ、大気中のCO₂濃度は現在よりも大幅に高くなり、地球温暖化が加速すると考えられている。
また、炭素循環の一環として、プランクトンの死骸が堆積して堆積岩(石灰岩や白亜など)を形成することもある。例えば、白亜紀の地層には円石藻や有孔虫の遺骸が大量に含まれており、長期的な炭素隔離の役割を果たしている。
プランクトンの減少が環境に与える影響
近年、気候変動や海洋汚染によってプランクトンの量が減少しつつある。プランクトンの減少は、以下のような影響をもたらす:
- 海洋食物連鎖の崩壊 - プランクトンの減少により、魚類やクジラなどの大型生物の生息数が減少する。
- 酸素供給の減少 - 光合成量の低下により、大気中の酸素供給に悪影響を及ぼす。
- 炭素固定の低下 - CO₂の吸収能力が低下し、地球温暖化の加速につながる。
このように、プランクトンの減少は生態系だけでなく、地球環境全体に大きな影響を与えるため、その保全が非常に重要である。
研究者たちは、プランクトンの動態を観測しながら、地球温暖化や海洋汚染の影響を予測することで、持続可能な環境保護のための対策を模索している。特に、海洋酸性化や温暖化がプランクトンの分布に与える影響を評価する研究が進められている。
プランクトンの分布と変動要因
プランクトンは、地球上のあらゆる水域に分布しているが、その分布や量はさまざまな要因によって変動する。光の強さ、栄養塩の供給量、水温、海流といった環境要因がプランクトンの成長や増減に大きく影響を与える。
また、季節による変動や、赤潮やアオコなどの異常発生現象が見られることもあり、これらは水質や生態系に影響を及ぼすことがある。近年では、地球温暖化による海洋環境の変化がプランクトンの分布や生態に影響を与えており、その動向が注目されている。
分布の要因(光・栄養・水温・海流)
プランクトンの分布を決定する主な要因は以下の4つである。
- 光(光合成に必要なエネルギー)
- 栄養塩(窒素・リン・ケイ素などの無機栄養)
- 水温(成長速度や代謝に影響)
- 海流(プランクトンの移動や混合)
光の影響
植物プランクトンは光合成を行うため、光が届く範囲(表層のフォトシンセティックゾーン)に多く存在する。光の強さは水深が深くなるほど減少するため、深海ではほとんどの植物プランクトンが生息できない。
また、海水の透明度によっても光の届く範囲は異なり、透明度が高い外洋では深い層まで光が届く一方、沿岸部では濁りがあるため、浅い水域に限られる。
栄養塩の影響
プランクトンの成長には、窒素(N)、リン(P)、ケイ素(Si)といった栄養塩が必要である。特に、珪藻はシリカ(ケイ素)を利用して細胞壁を形成するため、シリカの供給が制限されると成長が阻害される。
栄養塩の供給は以下のような要因によって決まる:
- 河川からの流入(沿岸部に栄養が多い理由)
- 深層水の湧昇流(アップウェリングによる栄養供給)
- 動物プランクトンの排泄物(再生栄養)
水温の影響
水温はプランクトンの生理機能に大きな影響を与える。一般的に、水温が高いと代謝が活発になり、増殖速度が上がるが、特定の種は低温環境を好むものもいる。
水温の違いによるプランクトンの分布の特徴:
- 寒冷域:大型の珪藻やオキアミが多い
- 温帯域:珪藻と渦鞭毛藻が混在
- 熱帯域:小型のシアノバクテリアや渦鞭毛藻が優勢
海流の影響
海流は、プランクトンの移動に大きく影響を与える。例えば、暖流域では生産性が低く、寒流や湧昇流が発生する場所では栄養が豊富でプランクトンの増殖が活発である。
代表的な海流の影響:
- ペルー海流(フンボルト海流) - 湧昇流が発生し、世界有数の豊かな漁場を形成
- 黒潮 - 水温が高く、栄養塩が少ないため、プランクトンの密度が低い
季節変動と赤潮・アオコなどの現象
プランクトンの量は季節によって大きく変動し、春や秋に増加することが多い。この現象は「春季ブルーム」と呼ばれ、光が強くなり、水温が上昇し、栄養塩が豊富な状態になると爆発的に増殖する。
赤潮(有害藻類ブルーム)
赤潮は、特定のプランクトンが異常繁殖する現象で、水の色が赤褐色や緑色に変化し、魚介類の大量死を引き起こすことがある。
赤潮の主な原因は以下の通り:
- 渦鞭毛藻の異常増殖(例:アレキサンドリウム属の発生)
- 富栄養化(窒素やリンが大量に供給される)
- 水温上昇(高温環境で増殖が加速)
アオコ(ブルーム)
アオコ(シアノバクテリアの大量発生)は、湖沼やダム湖で発生しやすい。シアノバクテリアは窒素固定を行うため、栄養豊富な環境では急激に増殖する。
特に夏季に発生しやすく、毒素を産生する種(例:マイクロシスチン)による水質悪化や生物への影響が懸念される。
地球温暖化による影響
地球温暖化によって海水温が上昇すると、プランクトンの分布や生態系が大きく変化する可能性がある。
- 温暖化に伴い、温水を好むプランクトンが北上
- 高水温による酸素濃度の低下が、生物の生存に影響
- 海洋酸性化が珪藻や円石藻の成長を阻害
特に、CO₂の増加による海洋酸性化は、石灰質の殻を持つプランクトン(円石藻や有孔虫)に深刻な影響を与えるとされており、これが海洋の炭素循環に及ぼす影響が懸念されている。
このように、プランクトンの分布と変動要因は非常に多様であり、環境の変化に対する指標としても重要な役割を果たしている。
プランクトンの採集と研究方法

プランクトンは水界生態系において重要な役割を果たしており、その研究は海洋学や生態学、環境科学の分野で広く行われている。プランクトンの採集・観察・分類には、専用のネットを用いた物理的な採集方法や、顕微鏡観察、DNA解析、蛍光測定などの高度な技術が活用されている。
これらの研究方法を用いることで、プランクトンの種類や分布、生態系への影響、気候変動との関係を明らかにすることが可能になる。
プランクトンネットによる採集
プランクトンの採集には、専用のプランクトンネットが用いられる。このネットは、目の細かいメッシュを持ち、水中を引いてプランクトンを濃縮し、採集するための装置である。
プランクトンネットの構造
一般的なプランクトンネットは以下のような構造を持つ:
- 円形の枠(ネットを広げるための金属またはプラスチック製のフレーム)
- 細かいメッシュの円錐状ネット(0.1mm〜0.33mmなどの異なる目合いを使用)
- 先端のサンプルボトル(プランクトンを集めるためのガラスまたはプラスチック容器)
採集方法
プランクトンネットを用いた採集方法には以下のような手法がある:
- 鉛直採集:ネットを水深の深い位置まで沈め、ゆっくりと引き上げる方法。深海のプランクトンを採集する際に使用される。
- 水平採集:一定の深さでネットを水平に引く方法。特定の水層にいるプランクトンの分布を調べるのに適している。
- 表層採集:水面付近のプランクトンを採集する方法。赤潮やアオコの発生調査に利用される。
これらの方法を適切に組み合わせることで、さまざまな水深や環境に生息するプランクトンのデータを収集することができる。
顕微鏡観察と分類
採集したプランクトンは、光学顕微鏡や電子顕微鏡を用いて観察・分類される。プランクトンの種類や形態を特定し、生態系内での役割を明らかにするために重要な手法である。
光学顕微鏡を用いた観察
光学顕微鏡を用いることで、微細なプランクトンの形態を観察できる。特に、以下のような分類が行われる:
- 植物プランクトン:珪藻、渦鞭毛藻、シアノバクテリアなど
- 動物プランクトン:カイアシ類、ミジンコ、クラゲ幼生など
染色や特定の試薬を用いることで、細胞の内部構造やDNAの特定部位を可視化することも可能である。
電子顕微鏡による詳細観察
光学顕微鏡では観察が困難な微細構造を調べるために、走査型電子顕微鏡(SEM)や透過型電子顕微鏡(TEM)が使用される。これにより、珪藻のシリカ殻や、円石藻の微細構造を高倍率で解析することができる。
DNA解析や蛍光測定を用いた研究方法
近年のプランクトン研究では、DNA解析や蛍光測定技術を活用することで、より正確な分類や動態解析が可能になっている。
DNA解析による分類
DNAバーコーディング技術を用いることで、形態だけでは判別が難しいプランクトンの種類を特定できる。手順は以下の通り:
- プランクトンサンプルからDNAを抽出
- 特定の遺伝子領域(例:rRNA遺伝子)をPCR増幅
- シーケンシングによる塩基配列の決定
- データベースと照合し、種を特定
この技術は、未記載の新種の発見や、環境変化によるプランクトンの動態解析に役立つ。
蛍光測定を用いた研究
プランクトンの生理活動をリアルタイムで調査するために、蛍光測定技術が利用される。代表的な方法として、以下のような手法がある:
- クロロフィル蛍光測定:植物プランクトンの光合成活性を測定
- 蛍光顕微鏡による観察:特定のタンパク質や細胞内成分を可視化
- フローサイトメトリー:個々のプランクトン細胞を自動解析し、種や活動状態を評価
これらの技術を活用することで、環境変化がプランクトンに与える影響を詳細に解析することが可能となる。
最新の研究動向と今後の展望
近年、人工知能(AI)や機械学習を用いたプランクトンの自動分類技術が発展しており、これにより大量のデータを迅速に処理できるようになっている。また、環境DNA(eDNA)を利用した非侵襲的なモニタリング手法も注目されている。
これらの技術の進歩により、プランクトンの生態動態や気候変動の影響をより正確に把握し、生態系の管理や保全に役立てることが期待されている。

まとめ
プランクトンは、水界生態系の基盤を形成し、地球の炭素循環や酸素供給など、多くの重要な役割を担っている。植物プランクトンは光合成を通じて酸素を供給し、動物プランクトンは食物連鎖の中で多様な生物の栄養源となる。また、バクテリオプランクトンやウイルスプランクトンも分解者として生態系の物質循環に貢献している。
プランクトンは、水温や光、栄養塩、海流などの環境要因によって分布が大きく変動する。また、赤潮やアオコなどの現象は、環境の変化がプランクトンの異常増殖を引き起こすことを示している。さらに、地球温暖化による影響も顕著になりつつあり、今後の生態系への影響が懸念されている。
プランクトンの研究は、プランクトンネットによる採集、顕微鏡観察、DNA解析、蛍光測定といった多様な手法を用いて行われている。近年では、環境DNA(eDNA)解析やAIを活用した自動分類技術も進展しており、より精密な研究が可能になっている。
これらの研究成果を活かし、プランクトンの変動をモニタリングすることで、環境変化の早期警戒システムとして活用することも期待されている。特に、海洋の炭素吸収能力の評価や、漁業資源管理への応用など、多岐にわたる分野での応用が進んでいる。
今後も、プランクトンの研究を通じて、地球環境の変動を理解し、持続可能な水界生態系を維持するための科学的知見を蓄積していくことが求められる。プランクトンの観察と解析を続けることで、私たちの未来に向けた重要な手がかりを得ることができるだろう。