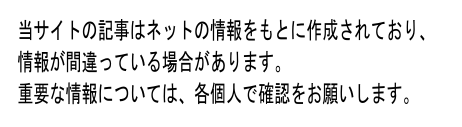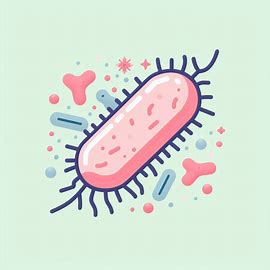
ビフィズス菌とは何か
ビフィズス菌は、人間を含む多くの動物の腸内に生息している細菌であり、健康維持に大きく関与していることから、近年注目が高まっているプロバイオティクスのひとつです。
とくに乳児期の腸内環境においては、ビフィズス菌が優勢な腸内細菌群を形成することで知られており、腸内フローラの健全な発達に寄与しています。
ここでは、ビフィズス菌の分類、生物学的な特徴、名称の由来と混同されやすい呼び名について詳しく解説します。
グラム陽性の偏性嫌気性桿菌であること
ビフィズス菌は、細胞壁の構造においてグラム陽性に分類される桿菌であり、酸素を嫌う偏性嫌気性の性質を持っています。
このため、通常の大気中では生育が難しく、酸素の存在しない環境、すなわち腸管内のような無酸素条件下でよく増殖します。
形態的には直線的な桿状ではなく、Y字やV字型に分岐する独特の形状を示すことが特徴です。
この形状こそが「ビフィズス(bifidus)」という名前の由来にもなっています。
放線菌綱・Bifidobacterium属に属する細菌の総称
分類学的には、ビフィズス菌は放線菌綱(Actinobacteria)の中に位置づけられており、Bifidobacteriales目、Bifidobacterium属に属する細菌群を指します。
この属には多数の菌種が含まれており、ヒトの腸内で主要な役割を果たす種としては、B. bifidum、B. breve、B. longum、B. infantis、B. adolescentisなどが知られています。
これらの菌種は、宿主の年齢や栄養状態によって腸内における比率が異なる傾向にあります。
ビフィズスという名称の由来(Bacillus bifidus → Bifidobacterium bifidum)
ビフィズス菌の発見は1899年、フランスのパスツール研究所に所属していた小児科医アンリ・ティシエによるもので、彼は乳児の糞便中からこの菌を分離しました。
その際、菌体が二又に分岐することから、ラテン語で「二又の」という意味を持つbifidusという語が用いられ、当初はBacillus bifidus(バチルス・ビフィドゥス)と命名されました。
その後、1924年にデンマークのOrla-Jensenによって新たにBifidobacterium属が創設され、この種はBifidobacterium bifidumへと再分類されました。
この名称の変遷が、現在でも「ビフィズス菌」と「ビフィダム菌」という二つの呼び方の混同を招く原因となっています。
種名と通称(ビフィダム菌との混同も含めて)
本来、「ビフィズス菌」という名称は、Bifidobacterium属全体を指す通称として使われています。
しかしながら、歴史的経緯から、特にBifidobacterium bifidumのみを指して「ビフィズス菌」と呼ぶケースも少なくありません。
このため、特に学術的または医療的な文脈では、正確な菌種名を明示することが求められます。
また、市販のヨーグルト製品やサプリメントでは、B. bifidumだけでなく、B. longumやB. breveといった他の菌種も含まれていることがあり、消費者が名称だけで内容を正しく理解するのは難しい場合があります。
したがって、通称と分類学上の名称を正確に使い分ける意識が重要です。
ビフィズス菌の発見と分類の歴史
ビフィズス菌は、腸内細菌の研究において非常に重要な存在として長い歴史を持つ細菌です。
その発見と分類は、20世紀初頭の細菌学の進展と密接に関連しており、今日に至るまで継続的に再評価と再分類が行われてきました。
この章では、ビフィズス菌の科学的発見から、現在のBifidobacterium属への分類に至るまでの過程を詳しく解説します。
1899年、H.ティシエによる乳児糞便からの発見
1899年、フランスのパスツール研究所に所属していた小児科医アンリ・ティシエ(Henri Tissier)は、母乳で育てられた乳児の糞便中から独特な細菌を発見しました。
この細菌は、従来知られていた大腸菌とは異なる性質を持ち、乳酸を産生することから、乳児の健康と密接な関係があると考えられました。
この発見は、腸内細菌叢の構造や機能についての理解を大きく前進させるきっかけとなりました。
bifidus(Y字型の形態)という語の採用
ティシエが発見した菌は、顕微鏡観察の結果、Y字型やV字型に分岐した特異な形状を示していました。
この特徴的な形態から、ラテン語で「二又の」や「分岐した」を意味するbifidusという語が採用され、当初はBacillus bifidus(バチルス・ビフィドゥス)という名前が付けられました。
この「bifidus」という語が、現在でも「ビフィズス菌」という呼称に使われている語源です。
1924年、Orla-Jensenによる再分類と属名の変更
その後の研究により、この菌が従来のバチルス属とは異なる特徴を持つことが明らかになり、1924年にデンマークの細菌学者オーラ・イェンセン(Orla-Jensen)が新たな属名を提案しました。
彼は、「bifidus(分岐)」と「bacterium(細菌)」を組み合わせてBifidobacteriumという新属を設立し、ティシエが発見した菌はBifidobacterium bifidumとして再分類されました。
この再分類により、ビフィズス菌は独立した分類群として認識されるようになったのです。
ラクトバチルス属からの独立と名称の変遷
再分類以前は、ビフィズス菌はその乳酸生成能から、Lactobacillus属(ラクトバチルス属)に近い存在と見なされていた時期もありました。
実際、1960年代以前にはLactobacillus bifidusという表記が使われることもありました。
しかしながら、細胞壁構造や代謝経路の違いなどから、現在ではBifidobacterium属は放線菌綱に属し、ラクトバチルス属とは明確に区別される分類群とされています。
このように、ビフィズス菌は長年にわたる科学的探究の中で、その存在意義と分類学的位置付けが大きく変化してきた菌種であることがわかります。

人間の腸内におけるビフィズス菌の種類と分布
ビフィズス菌は、人間の消化管に自然に定着する腸内常在菌の中でも特に重要な役割を担っており、乳児から高齢者までのライフステージにわたってその種類と比率が変化します。
特に乳児期には、腸内の善玉菌の多くをビフィズス菌が占めており、その優勢な存在が健康な腸内フローラの形成に貢献しています。
また、近年では特定の菌株を商業的に活用する動きも進んでおり、食品・サプリメント業界においても注目を集めています。
代表的な5種(B. bifidum、B. breve、B. longum、B. infantis、B. adolescentis)
ヒトの腸内に常在するビフィズス菌には多数の種がありますが、中でも頻繁に確認される代表的な5種は以下の通りです。
- Bifidobacterium bifidum(ビフィドゥム種):1899年にティシエが発見した基準種。成人の腸内にも広く存在します。
- Bifidobacterium breve(ブレーベ種):小型の桿菌で、乳児期に多く確認されます。
- Bifidobacterium longum(ロンガム種):幅広い年齢層で見られる菌で、消化器系への適応力が高いとされています。
- Bifidobacterium infantis(インファンティス種):乳児の腸内に特に多く分布しており、母乳由来の糖を効率的に代謝できます。
- Bifidobacterium adolescentis(アドレセントゥリス種):思春期から成人期にかけて増加傾向を示す菌種です。
これらの種は年齢や食生活に応じて腸内での存在比率が変化し、それぞれのライフステージで異なる役割を果たしています。
母乳栄養児の腸内での優勢な存在
母乳栄養児の腸内では、ビフィズス菌が他の細菌に比べて圧倒的に多く、腸内細菌叢の大部分を占めています。
これは母乳中に含まれる乳糖やオリゴ糖が、ビフィズス菌の増殖を助ける「ビフィズス因子」として機能するためです。
とくにB. infantisは母乳由来のヒトミルクオリゴ糖(HMO)を効率よく代謝できる特性があり、乳児の腸内環境の形成に不可欠な存在といえます。
そのため、出生後間もなく母乳を摂取することが、健全な腸内細菌叢の確立に大きく寄与すると考えられています。
ヒト以外の動物におけるビフィズス菌の分布例(B. animalisなど)
ビフィズス菌はヒトだけでなく、哺乳類全般の腸管にも広く分布しています。
なかでもBifidobacterium animalisは、多くの哺乳動物の大腸に共通して見られる種であり、ヒト由来の菌とは異なる特徴を持ちます。
この種は、酸や酸素に対して比較的高い耐性を示すため、食品加工にも適しています。
そのため、動物由来であっても乳酸菌製品やヨーグルトなどに応用される機会が多くあります。
菌株による商標(BB-12、BB536など)
近年では、同一種であっても異なる機能性を持つ個別の菌株に注目が集まり、企業によって独自の番号やアルファベットを付した商標化が進んでいます。
代表的なものとしては以下が挙げられます。
- BB-12:B. animalis subsp. lactisの一菌株で、デンマークのクリスチャン・ハンセン社が開発。
- BB536:B. longumの菌株で、森永乳業が特定保健用食品や機能性表示食品に応用しています。
- GCL2505(BifiX):グリコが使用する菌株で、酸や胆汁への耐性に優れることが特徴。
このような商標化は、科学的根拠に基づいた機能性を明示しつつ、他社製品との差別化を図る重要な手段となっています。
ビフィズス菌の代謝と酸素への応答
ビフィズス菌は腸内という特殊な環境に適応した細菌であり、その代謝経路や酸素への反応は他の一般的な乳酸菌とは異なる特徴を持っています。
特に注目されるのが、糖質を分解する際の特異な代謝機構と、酸素存在下での成長特性です。
この章では、ビフィズス菌のエネルギー獲得手段である代謝経路と、酸素に対する感受性の違いについて詳しく解説します。
糖を分解して乳酸・酢酸を生成するヘテロ乳酸発酵
ビフィズス菌は、糖質を分解して乳酸と酢酸を産生する特徴的な発酵パターンを持ち、これをヘテロ乳酸発酵と呼びます。
この代謝により腸内のpHは低下し、病原性細菌の繁殖が抑制されるため、腸内環境の健全化に寄与します。
特に酢酸は腸管バリア機能の強化や抗菌作用において重要な役割を果たすとされており、乳酸単独の産生に比べてより多面的な健康効果が期待されます。
また、発酵によって得られるエネルギー効率は高く、低栄養環境でも安定した生存が可能です。
特異的な代謝経路(フルクトース-6-リン酸ホスホケトラーゼ経路)
ビフィズス菌の代謝は、他の多くの乳酸菌が利用する解糖系(EMP経路)とは異なり、フルクトース-6-リン酸ホスホケトラーゼ経路(F6PPK経路)を利用しています。
この経路では、1分子のグルコースから2分子の酢酸と1分子の乳酸を産生するため、酢酸比率の高い発酵が可能になります。
F6PPK経路はビフィズス菌特有の代謝機構であり、この点が乳酸菌一般との明確な違いとなっています。
この経路によって、ビフィズス菌は母乳や植物由来のオリゴ糖などを効率的にエネルギーへと変換できる能力を持ち、乳児期や食物繊維が豊富な食生活においてその存在感を高めています。
酸素感受性による分類(O2過敏型〜微好気性)とH2O2生成の影響
ビフィズス菌は偏性嫌気性菌として知られており、多くの菌株は酸素の存在下での成長が制限されます。
しかし、近年の研究では、菌株ごとに異なる酸素応答性を示すことが明らかとなっています。
これにより、ビフィズス菌は以下の4つのグループに分類されます。
- O2過敏型:酸素の存在でまったく成長できない。
- O2感受型:酸素濃度に強く影響されるが、わずかに成長可能。
- O2耐性型:ある程度の酸素濃度下でも成長が維持される。
- 微好気性型:低酸素状態で最も成長が促進される。
酸素が存在する環境では、ビフィズス菌が過酸化水素(H2O2)を産生することが知られており、これが成長阻害の一因と考えられています。
特にB. bifidumでは、酸素存在下でNADHオキシダーゼによりH2O2が生成され、これが菌の増殖を抑制してしまうことが報告されています。
そのため、ビフィズス菌をプロバイオティクスとして活用する際には、製造・保存・摂取の各段階で酸素への曝露を極力抑えることが重要です。
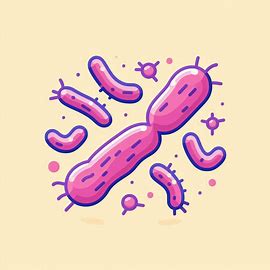
ビフィズス菌の健康への効果
ビフィズス菌は腸内環境の維持に寄与するだけでなく、免疫調整や感染症の予防、さらには慢性疾患の補助的治療にも関与するとして、医学的にも高い関心が寄せられています。
本章では、ビフィズス菌がもたらす代表的な健康効果について、科学的根拠をもとに詳細に解説します。
腸内pHの低下による腸内環境の改善
ビフィズス菌は糖質を代謝して乳酸や酢酸といった有機酸を生成し、腸内のpHを酸性に保ちます。
この酸性環境は、悪玉菌とされる腐敗菌や病原性細菌の増殖を抑制し、善玉菌が優勢な腸内フローラの形成を助けます。
腸内pHの低下は腸管バリア機能を強化し、便通の改善や免疫力の向上につながることが報告されています。
また、酢酸には抗菌作用があり、病原菌に対して直接的な防御効果を持つ点でも注目されています。
免疫調整作用やアレルギー症状(例:花粉症)への効果
ビフィズス菌は腸管に存在する免疫細胞との相互作用を通じて、全身の免疫応答に影響を及ぼすことが分かっています。
特に、腸管に存在するパイエル板や樹状細胞に働きかけて、免疫バランスを調整するとされています。
この作用により、過剰なアレルギー反応の抑制や、免疫過敏症状の緩和が期待されます。
実際に、ビフィズス菌を含むプロバイオティクスの摂取が、花粉症などのアレルギー症状を軽減する可能性があるという研究結果も報告されています。
感染性腸炎(ロタウイルスなど)の抑制作用
乳幼児に多いロタウイルスやノロウイルスによる感染性腸炎に対しても、ビフィズス菌の効果が注目されています。
ビフィズス菌は腸内において物理的なバリアを形成し、腸上皮への病原体の接着を阻害することが可能です。
また、抗菌物質の産生や宿主免疫の活性化を通じて、感染の拡大を防ぐメカニズムが考えられています。
特にB. breveやB. infantisなど乳児由来の菌種は、ロタウイルス感染時の下痢や発熱の抑制に有効であるとする臨床報告もあります。
プロバイオティクスとしての臨床応用(潰瘍性大腸炎、IBSへの可能性)
ビフィズス菌は、医療現場においてもプロバイオティクスとしての応用が進んでいます。
たとえば、炎症性腸疾患のひとつである潰瘍性大腸炎(UC)においては、通常治療にビフィズス菌を併用することで、症状の緩和や寛解維持に貢献する可能性が報告されています。
また、過敏性腸症候群(IBS)に対しても、腹部膨満感や痛みの軽減などの有効性が示唆されています。
こうした効果は、ビフィズス菌が腸内環境を整えるだけでなく、腸管神経系や免疫系との複雑な連携を通じて全身に作用していることを意味しています。
ビタミンの産生と栄養との関係
ビフィズス菌は腸内フローラのバランスを保つだけでなく、栄養学的な側面でも重要な機能を果たしています。
とくにビタミンの産生や蓄積という観点からは、腸内細菌の中でも注目される存在です。
この章では、ビフィズス菌が体内でどのようにビタミンと関わっているか、そしてその栄養的意義について詳しく解説します。
ビタミンB群や葉酸、ビタミンCの産生と蓄積
ビフィズス菌は、腸内でビタミンB群(B1、B2、B6、B12、ナイアシン、葉酸、ビオチンなど)やビタミンCを産生する能力を持っています。
特にB. infantis、B. breve、B. bifidum、B. longum、B. adolescentisといった代表的なヒト常在菌は、これらのビタミンを菌体内に蓄積すると同時に、外部にも一部放出します。
腸内で産生されたビタミンB2、B6、B12、葉酸の合計は、成人が1日に必要とする量の約14〜38%に相当するとの報告もあり、無視できない栄養供給源となっています。
パンテチンやリボフラビンの必要性
一方で、ビフィズス菌自身の生育には特定の栄養素が必要とされます。
とくにパントテン酸(ビタミンB5)は、ビフィズス菌ではパンテチンという中間代謝物の形でないと利用できないとされています。
また、リボフラビン(ビタミンB2)も外部からの供給が必要であり、この栄養要求性は菌株によって異なるものの、栄養設計や培養条件において考慮されるべき点です。
これらの栄養因子の供給状態が、腸内でのビフィズス菌の定着や活性を大きく左右する可能性があります。
腸内産生されたビタミンの吸収制限(特にビタミンB12)
ビフィズス菌によって産生されたビタミンのうち、腸内でヒトの体に吸収されるかどうかはビタミンの種類や吸収部位によって異なります。
たとえばビタミンB12は、小腸の終末部である回腸で「内因子」と結合した状態でなければ吸収できません。
しかし、ビフィズス菌がビタミンB12を産生するのは主に大腸であるため、このビタミンは腸内で産生されても人体に十分吸収されにくいという制限があります。
一方、葉酸やビタミンB2、B6などは大腸からの一部吸収が可能であるとされており、腸内ビタミン産生が栄養補助の役割を果たす可能性が示唆されています。

ビフィズス菌の食品利用と応用
ビフィズス菌は、その健康効果が広く認められるようになったことで、食品分野での応用が急速に進んでいます。
とくに発酵乳製品やサプリメントの分野では、消費者の腸内環境改善への関心とともに需要が高まり、さまざまな製品に活用されています。
この章では、ビフィズス菌の食品利用の歴史から、現在の商業的応用例、菌株の違い、機能性表示との関係までを解説します。
発酵乳への応用(1948年ドイツでの初利用)
ビフィズス菌が食品に応用された最初の事例は、1948年にドイツのマイヤー博士が製造した発酵乳製品であると記録されています。
この製品は、ビフィズス菌を乳酸菌とともに乳に添加し、発酵させて作られたもので、腸内環境の改善や乳児の健康増進を目的としていました。
当時としては画期的な取り組みであり、その後のヨーグルトやプロバイオティクス飲料の開発に大きな影響を与える先駆けとなりました。
乳児・成人向けヨーグルトやサプリメントへの応用例
現在では、ビフィズス菌は乳児用粉ミルク、ヨーグルト、飲料型発酵乳、サプリメントなど多岐にわたる製品に応用されています。
乳児向け製品には主にB. breveやB. infantisなど、母乳育児と相性の良い菌種が使用される傾向があります。
一方、成人向け製品では、耐酸性や定着性に優れるB. longumやB. lactis(動物由来)などが用いられています。
ビフィズス菌は製品ごとに期待される効果に応じて菌種や菌株が選ばれ、機能性を明示することで消費者の信頼を得ています。
ヒト由来株と動物由来株の利用の違い
ビフィズス菌にはヒト由来株と動物由来株が存在し、それぞれの特性に応じて用途が異なります。
ヒト由来株は、ヒトの腸内に定着しやすく、免疫調整作用や消化機能の改善などに適している一方で、培養や加工が難しい傾向があります。
一方、動物由来株(たとえばB. animalis subsp. lactis)は、酸や酸素に対して強い耐性を持つため、食品加工や長期保存に向いています。
安全性の確保や効果の一貫性を担保するため、商業的には動物由来株が多用される傾向にありますが、医療や特定用途ではヒト由来株の価値も高く評価されています。
食品機能表示や特定保健用食品(トクホ)との関連
ビフィズス菌を含む食品は、近年、機能性表示食品や特定保健用食品(トクホ)として市場で広く流通しています。
たとえば、B. longum BB536(森永乳業)やB. lactis BB-12(クリスチャン・ハンセン社)などは、科学的根拠に基づいて機能性が評価され、「腸内環境を整える」「便通を改善する」などの表示が許可されています。
こうした制度は、消費者にとって製品の選択基準となるだけでなく、企業にとっても品質と差別化の証として重要な要素となっています。